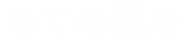今日はウニの豆知識をお伝えしたいと思います。
品質管理がとても難しいウニですが、お寿司やさん、スーパー、ネット通販というように今は直接目で見て買うことも、ネット上の情報で買うこともできます。そんな時に、ウニの表記方法に違いを感じたことのある方はいるのではないでしょうか。大きな違いとしては漢字表記なのかカタカナ表記なのか。
今日はウニを漢字で書いた時に、どんな意味の違いがあるのか見ていきましょう。
「ウニ」を漢字で書いた時の意味の違い
はじめに、「ウニ」は漢字で4つの書き方があります。
そしてそれぞれの漢字にはこのような意味が込められています。
①海栗・・・生きてる状態
②海丹・・・毬、生きてる状態
③海胆・・・殻から取り出した可食部の状態
④雲丹・・・加工した状態(塩ウニなど
①海栗
「海」という漢字と「栗(クリ)」という漢字を合わせて
「海栗(ウニ)」と読みます。
この字を使う時はウニが殻に入った状態でまだ生きてる状態のことをいうのですが、トゲトゲがついた状態のウニは確かに「クリ」にそっくりですよね。
海にある栗ということで覚えやすいかと思います。
言い換えるとするならば、「活ウニ」と言ってもいいかもしれません。

②海丹
イガイガを含めた生きている状態を指し、守備範囲の広い漢字です。
丹という漢字には赤い色という意味があり
ウニ の身が赤く見えることから、
この漢字で表されることになったそうです。
ムラサキウニは黄色に近い色で業界用語で「白」と呼ばれ、
バフンウニ はオレンジに近い色で業界では「赤」と呼ばれているので
海丹という漢字はバフンウニ から由来するのでしょうね

③海胆
この漢字は生のウニを表しています、
食べる時のプリッとした身を表しています。
うにの食べられる部分を
きも「胆(=肝)」と考え、
海胆と書くようになった。
正確には、ウニは肝を食べるのではなく
生殖巣を食べているのですが、下の写真は殻から取り出した可食部の状態、まさに「海胆」なのですが横から見たときの身の厚みが最高に美味しそうですよね。
この写真のウニは「大千(ダイセン)」という青森県のブランドウニなのですが、かねてより非常に人気と信頼の高い3大ブランドウニと称される
・はだての生うに
・東沢の生うに
・橘の生うに
に割って入り4大ブランドウニと呼ばれるまでに急成長した今最も波に乗っているウニです。
お寿司やさんなどで「ダイセンの生うに」を見かけた際は是非お試し下さい。
とっても美味しいですよ。

④雲丹
この字はウニを加工した状態を表しています。
僕はウニを漢字変換する際はこの文字を一番多く使いますが皆さんも一番目にする機会が多いのはこの文字なのではないでしょうか。
殻から取り出した生殖巣を
お酒や塩で加工した練ったうにのことを指しますが、
例えば、豊洲市場に入荷してくる沢山のウニもミョウバン水を使い
加工しているので雲丹という文字を使って表します。
この字は、中国渡来の言葉で、
栄養価の高い保存食品を、
医食同源の思想が主流の中国では薬とみなし、
「雲丹」と称したと言われています。
中国でも昔からウニが食べられていたなんて
驚きですね!

終わりに
普段何気なく使っていたウニは漢字では4パターンも書き方があり、
それぞれに意味があることを知る事ができました。
このことを知ってからというもの、漢字を見た時には、どんな意味だっけと思い返しながらウニの状態を想像するようにしています。
他にもウニと似たような事例が見つかりましたら共有させて頂きたいと思います。
魚屋が大切な家族に本当に食べさせたいお魚をご自宅にお届け
魚河岸が日本橋に所在を置いていた時代から約130年間。
日本橋・築地・豊洲と何度も場所を変えいくつもの時代を超えて
沢山の同業者やお客様と築いてきた信頼と実績で最高のお魚をお選びします。
yusaku